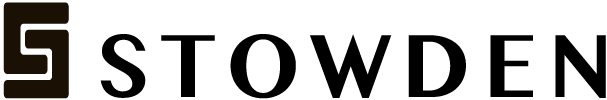キッチンの中でも特に使う頻度が高いのが食器棚ですが、開き戸タイプの収納はその設計や使い方によって、利便性が大きく左右されます。
食器棚収納の基本として「どこに何を入れるか」の判断は、調理や片付けの効率に直結する重要なポイントです。食器棚の奥が取りにくい、奥行きがある食器棚の収納方法がわからない、観音開きの食器棚収納が使いにくいといった声も多く、収納方法の見直しが求められています。
本記事では、食器棚収納を見直したいと考える方に向けて、観音開きの食器棚が抱える使いにくさや、カップボードの開き戸から引き出し式への変更といった実用的なアイデアを含め、100均収納術を活用した食器棚収納術の具体例を多数ご紹介します。収納グッズや配置の工夫によって、引き出し式収納方法を取り入れるだけでなく、シンプルで快適な動線をつくることが可能です。
日常的な使いやすさはもちろん、安全性や家族構成への配慮も踏まえた情報を盛り込み、すぐに実践できる内容に仕上げています。食器棚収納に悩んでいる方や、少しでも快適なキッチンを目指したい方にとって、参考になるヒントがきっと見つかるはずです。
- 開き戸タイプの食器棚を効率よく使うための収納方法がわかる
- 奥行きのある棚や奥のスペースの活用術が理解できる
- 100均アイテムを使った実践的な収納術が学べる
- 引き出し式との比較や改造方法、安全対策まで把握できる
開き戸タイプの食器棚収納術

ストウデン・イメージ
- 収納の基本。どこに何を入れる?
- 奥のほうが取りにくい問題を解決
- 奥行きがある食器棚の収納方法
- 100均活用の収納術
収納の基本。どこに何を入れる?

ストウデン・イメージ
食器棚の使いやすさを大きく左右するのは、「どこに何を入れるか」という収納の配置です。使う頻度や使用タイミングを考慮して収納場所を調整することで、必要な物がすぐに取り出せるだけでなく、戻す動作もスムーズになるため、キッチン全体の動きが格段に良くなるからです。
例えば毎日使用するお皿やコップ類は、腰の高さに近い中段に置くと取り出しやすくなります。この高さは身体への負担が少なく、自然な動作で出し入れができるため、時短にもつながります。重量があって出番の少ない土鍋や大きめの鍋などは、下段のスペースにまとめて配置することで安全面が向上します。あまり使わない来客用の食器や非常用の紙皿などは上段に収納すると、普段の動線を邪魔しません。
このように上・中・下のそれぞれの段を役割ごとに分けて活用することが、収納の効率を上げる鍵となります。棚板の高さが調整可能なタイプであれば、収納するアイテムの高さに合わせて柔軟に調整すると、無駄なスペースが生まれにくくなります。
「使う人の動き」と「収納する物の特性」の両方を意識してエリア分けを行うことで、必要なものがすぐに見つかり、探す手間を大幅に減らすことができます。毎日のキッチン作業が快適になり、家事へのストレスも軽減されるでしょう。
目から腰の高さは「ゴールデンゾーン」とも呼ばれ、もっとも取り出しやすく収納効率が高いため、頻繁に使うものはこの位置に集めるのが理想的です。小さな子どもがいる家庭では、子ども用の食器は下段に配置することで自分で出し入れしやすくなり、家族全体の使いやすさも向上します。また、コの字ラックや持ち手付き収納ケースなどの便利な収納アイテムを使うことで、より効率的で整理された空間を実現できます。
奥のほうが取りにくい問題を解決

ストウデン・イメージ
開き戸の食器棚において多くの人が感じる悩みのひとつに、奥に収納した物が取りにくいという問題があります。特に奥行きのある棚や仕切りが少ない設計の場合、奥の食器や調理器具が見えづらく、取り出す際に手間がかかることがよくあります。これが積み重なると、使い勝手に不満を感じるようになり、せっかくの収納スペースがストレスの原因になってしまうのです。
このような不便を解消するためには、スライド式トレーや引き出せるラックの導入が非常に効果的です。これらのアイテムを活用することで、棚の奥にしまった食器類も手前に引き出して一目で確認できるようになります。例えばダイソーやセリアなどの100円ショップでは、「スライド式収納トレー」や「フリーザースタンド」などの実用的な商品が手軽に購入できます。
これらはキッチンの棚にそのまま置くだけで使えるため、取り付け工事などは不要です。収納トレーを活用すれば、毎日の料理や片付けの際にスムーズな動線が生まれ、時間と労力の節約にもつながります。
さらに応用的な方法として、棚に後付けできるレールや段差ラック(例:ニトリの「引き出し式バスケット」や山善の「棚上ラック」など)を組み合わせることもおすすめです。これにより、収納スペースの上下を有効に使いながら、視認性と取り出しやすさを両立できます。
また収納する物をジャンルごとに分け、持ち手付きバスケットやラベルを貼ったトレーなどで分類しておくと、どこに何があるかが一目で分かるため、探す手間も大幅に軽減されます。
収納の工夫は必ずしも大掛かりなリフォームを必要としません。ちょっとしたアイテムを追加するだけで、開き戸の食器棚が格段に使いやすくなる可能性があります。自宅のキッチンの構造やライフスタイルに合わせて、ぜひ取り入れてみてください。
奥行きがある食器棚の収納方法

ストウデン・イメージ
奥行きのある棚は収納力の面では魅力的ですが、前述の通りそのまま使うと奥に物を押し込んでしまいがちで、使いこなすのが難しいと感じることもあります。このような収納スペースを上手に活かすためには、「奥行きに合わせたアイテム選び」と「奥行きを意識した配置方法」がポイントになります。
まず奥行きの深い棚では、収納する物の奥行きも意識して選ぶと効果的です。例えば、奥行きが短い小皿やグラス類は手前に、奥行きのある鍋や保存容器などは奥側に配置することで、見た目も整い出し入れの際の混乱を防げます。
また、収納物の高さや形状に応じて棚の中を上下に区切る「中間棚」や「可動棚」を活用することで、縦方向にも空間を有効活用できます。中でも高さのある器やボトル類などは、奥行きを活かしつつ安定して収納するのに適しています。
棚奥にしまうものはラベルを付けたボックスやケースなどにまとめておくと、内容物がわかりやすく、必要なときに手早く取り出すことができます。こうした工夫を加えることで、奥行きのある食器棚でも「しまいやすく、見つけやすく、戻しやすい」収納が実現します。
奥行きという特性を活かしたアイテム選びと配置の工夫を取り入れることで、収納の使い勝手が向上し、見た目にも整ったキッチン空間を保つことができます。
100均活用の収納術

ストウデン・イメージ
手軽に始められる収納改善策として、100均アイテムの活用は非常に有効です。近年では、機能性だけでなくデザイン性にも優れた商品が増えており、初心者でも手軽に取り入れやすくなっています。主に仕切りケース、小物収納ボックス、すべり止めシート、段差ラック、ファイルボックスなどがあり、それぞれの特徴を活かすことで食器棚内の収納力を大きく高めることができます。
仕切りケースを使えば、お皿やカップの種類ごとに分けて収納でき、取り出す際の迷いを防げます。また、小さなカップを透明のボックスでまとめることで、見た目もすっきりし、在庫の確認も一目で可能です。段差ラックを活用すれば、奥のスペースを有効に使いながら、上下でアイテムを分けることができ、収納力がアップするだけでなく視認性も良くなります。
さらに、すべり止めシートを棚に敷くことで、出し入れの際に食器が滑るのを防ぐことができ、安全性も高まります。ファイルボックスを応用してトレー代わりに使えば、奥行きのある棚でも手前に引き出して中身を確認できるため、取り出しやすさが格段に向上します。
100均アイテムの活用ポイント
- 仕切りケース:
食器を形状ごとに分けて収納することで、破損リスクを軽減しつつ取り出しやすくなります。 - 小物収納ボックス:
調味料やカトラリーなど細かいものをまとめ、棚内をすっきり保てます。 - 段差ラック:
棚内を上下に分けることで視認性が高まり、デッドスペースの有効活用にも効果的です。 - すべり止めシート:
ガラス製の器やトレーが滑らないようにし、安全性を確保します。 - ファイルボックス:
大皿やパッケージ食品を立てて収納する際に便利で、奥行きのある棚でも出し入れしやすくなります。
デザイン性も高く、どんなインテリアにもなじむシンプルなアイテムが多いため、まずは一つの棚から試してみると、その便利さを実感できるでしょう。
食器棚の開き戸収納に関する注意点

ストウデン・イメージ
- 観音開き扉だと使いにくい?
- カップボードの開き戸を引き出しへ改造できる?
- 引き出し式収納との比較
- 開き戸収納で気をつけたいこと
観音開き扉だと使いにくい?

ストウデン・イメージ
観音開きの扉は、左右に大きく開くことができるため中の収納物を一目で確認しやすく、見た目もすっきりしていてデザイン性が高いため、インテリアとしても人気のあるスタイルです。しかし、実際に日常のキッチン作業で使用するとなると、いくつかの使いにくさを感じる場面もあります。
まず、観音開きは両手を使って扉を開け閉めする必要があるため、調理中で片手がふさがっている場合などにはやや不便さを感じることがあるでしょう。特に忙しい朝や複数の作業を同時進行しているときには、扉を開けるだけでも手間に感じてしまいます。
また開けた扉が前方に大きく開くため、キッチンの通路や周囲の動線に干渉してしまうこともあり、設置する場所を慎重に選ばなければなりません。
壁に近い場所や冷蔵庫の横、調理台のすぐ隣など日常的に人が行き来する場所の近くに観音開きを設置すると、扉を開けたときにぶつかる可能性が高くなります。小さなお子さまがいる家庭では、開けた扉にぶつかってしまうなどのリスクも考慮する必要があります。このような環境では、引き戸や引き出し式の収納のほうが開閉スペースを取らず作業の流れを妨げにくいため、より実用的な選択肢となるでしょう。
このように、観音開き扉は見た目や収納性に優れた面がある一方で、使用環境によってはデメリットも生じるため、設置の際には実際の動線や家族構成なども考慮したうえで検討することが大切です。
カップボードの開き戸を引き出しへ改造できる?

ストウデン・イメージ
一部のカップボードは、DIYや専門業者によるリフォームを通じて、開き戸から引き出し式の収納に変更することが可能です。たとえば、カインズではダンパー付きの「静かにしまる スライドレール」シリーズなど、DIY向けの後付けスライドレールが販売されています。
ニトリでは、カラーボックス専用の後付け引き出しレールがあり、別売りの収納ボックスと組み合わせて引き出し式収納として活用できます。これらを活用すれば、比較的手軽に収納を引き出し式へと変更することが可能です。
DIYに自信がない場合でも、リフォーム業者に依頼することで対応してもらえるケースが多く、ニーズに応じた柔軟な施工が選べます。こうした変更によって得られる最大のメリットは、奥まで手が届きやすくなり、収納効率が大きく向上する点です。特に深さのある棚では、引き出し式にすることで奥の物も視認しやすく、取り出しやすくなります。
この改造によって収納の中身が一目で確認できるようになるため、探し物にかかる時間を短縮できるだけでなく、物の管理もしやすくなります。仕切りやトレーを組み合わせることで、引き出し内の空間をさらに効率的に活用できるようになります。
ただし、こうした変更にはいくつかの注意点もあります。引き出し式への改造には、棚のサイズや素材に合わせた加工が必要になるため、DIYに慣れていない方にはややハードルが高い作業になることもあります。費用面でも、スライドレールの導入や引き出し本体の取り付け、必要に応じた補強工事などでコストがかかる可能性があります。
市販されている後付けタイプの引き出しレールを使用すれば比較的簡単に変更することもできますが、設置方法によっては耐荷重に制限があるため、重たい鍋やガラス製の器などを収納する場合には注意が必要です。
引き出し式収納との比較

ストウデン・イメージ
引き出し式収納には、奥の物まで一目で確認できてスムーズに取り出せるという明確な利点があります。引き出す動作ひとつで収納物全体が見渡せるため、使いたいものをすぐに見つけられ、取り出す際の無駄な動作が減ります。
特に、深さのある収納スペースではこの特性が際立ち、時間や手間の削減につながります。仕切りや小物用トレーと組み合わせれば、整頓された収納空間を維持しやすくなる点も魅力です。
一方で開き戸タイプにも独自のメリットがあります。見た目がすっきりしていて、扉の内側までフラットに掃除しやすく、定期的な清掃が行いやすいという点が特徴です。棚の中に段を設けることで、収納するアイテムの高さに応じて配置を柔軟に変えられるのも利点です。また、扉を全開にすれば全体を見渡すことができるため、大きめの食器や調理器具の出し入れにも適しています。
このように言うと引き出し式のほうが多機能に感じられるかもしれませんが、収納する物のサイズや種類、使用頻度、そしてキッチンのレイアウトや生活スタイルによって適した形式は変わります。例えば、頻繁に使用する小物や調味料などは引き出し式が便利ですが、大皿や鍋などの大型アイテムには開き戸収納のほうが向いている場合もあります。
どちらが良いかを判断する際には、見た目の好みや掃除のしやすさ、使う人の身長やキッチンの動線など、さまざまな要素を総合的に考慮することが重要です。必要に応じて両者を組み合わせた収納設計にするのも、非常に効果的な方法と言えるでしょう。
開き戸収納で気をつけたいこと

ストウデン・イメージ
開き戸収納では、収納力や見た目の整頓性だけでなく、安全面にも十分な配慮が必要です。扉の開閉動作が伴うため、物の落下や扉のぶつかりによる衝突など、日常の中で起こりうる小さな事故のリスクを考慮しておくべきです。特に、扉を勢いよく開けた際に棚の中の食器が揺れて倒れてしまったり、手前に出ていたものが落ちたりすることがあるため、収納物の安定性も重要です。
特に子どもがいる家庭では、安全対策をさらに強化する必要があります。チャイルドロックを扉に取り付けておけば、小さな子どもが誤って扉を開けて中の物を取り出したり、指を挟んでしまったりするリスクを軽減できます。また、扉の角が子どもの顔の高さに位置する場合もあるため、コーナークッションなどの安全グッズを併用することで、万一のケガを防ぐ工夫が求められます。
開き戸は開けた状態で空間を占有するため、近くの壁や家具にぶつかって傷をつけてしまうこともあります。これを防ぐには、扉が一定の位置で止まるようにするストッパーを取り付けるのが有効です。マグネットタイプやクッション性のあるストッパーなど、扉の材質や使用状況に合わせて適切なものを選ぶとよいでしょう。
このように安全面をしっかりと考慮したうえで収納設計を行うことが、安心して使い続けられるキッチン環境につながります。収納の見た目や利便性だけでなく、家族全員が安全に使える工夫を取り入れた収納計画を立てることが大切です。
安全対策の参考としては、こども家庭庁が公開している「事故防止ハンドブック」や、消費者庁による「こどもの事故防止」ページが非常に役立ちます。
食器棚の開き戸、収納のポイントを総まとめ
最後に整理術15選をまとめます。
- 使用頻度でゾーン分けする
毎日使う食器は中段、重い鍋は下段、来客用は上段に分ける - ゴールデンゾーンに日常使いの食器を配置
目から腰の高さに頻繁に使う物を集中させると効率的 - 棚板の高さを柔軟に調整する
収納物の大きさに合わせて棚を調整すれば空間を無駄にしない - コの字ラックで上下の空間を有効活用
小皿やカップを上下に分けてスッキリ収納 - スライド式トレーで奥の物を手前に引き出す
奥行きのある棚でも見渡しやすく、出し入れがラクになる - ジャンル別にバスケットで分類する
調理器具、カップ、カトラリーなどを種類ごとにまとめる - 100均の仕切りケースで見た目と安全性を両立
形がバラバラな器も仕切れば整然と並び破損リスクも減る - 段差ラックで視認性を高める
重ね置きしない収納で奥の物もひと目で見えるようにする - ファイルボックスを立て収納に活用
大皿やパッケージ食品を立てて出し入れを簡単に - ラベル付きケースで探し物ゼロに
何がどこにあるかが一目瞭然で時短につながる - 引き出し式収納へ改造して使いやすさUP
DIYや業者によるリフォームで奥の物も簡単に取り出せる - 観音開き扉は動線を意識して設置
冷蔵庫横や通路付近は開閉時に注意が必要 - チャイルドロックで子どもの安全を守る
誤開閉や指挟み事故を未然に防ぐ対策を取り入れる - 扉の角にコーナークッションを装着
子どもの顔の高さにある角を保護して安心な環境に - マグネットストッパーで扉の跳ね返りを防止
開きすぎや壁・家具との衝突を防ぎ長くきれいに保つ