メタルラックやスチールラックの棚板を追加したいけれど、純正パーツが高い、サイズが合わないと感じる方は多いです。そこで本記事では、スチールラックの棚板を使う方法だけでなく、棚板を100均素材で工夫する棚自作のアイデア、ニトリでの追加棚の入手可否、DIYパーツの種類、余った棚板の再利用、おしゃれに改造するコツ、スライド棚を後付けする手順、棚下のバスケット活用、ルミナススチールラックの特徴まで幅広く整理しました。
単に「置く場所を増やす」だけでなく、耐荷重・安全性・見た目のバランスを両立する考え方を、客観的な情報に基づいてまとめています。購入前の不安を減らし、無駄な出費を避けたい方にも役立つはずです。
- 自作と市販パーツを組み合わせた棚増設の全体像
- 低コストで仕上げる素材別の作り方と注意点
- 便利になる後付けオプションや収納強化アイデア
- 主要ブランドや公式情報を踏まえた選び方
メタルラック(スチールラック)の棚を自作で増やす
の棚を自作で増やす-。1-1024x981.jpg)
ストウデン・イメージ
- スチールラックの棚板の種類と選び方
- 棚板を100均素材で作る方法
- 棚を自作する前の採寸手順
- 棚増設を支えるDIYパーツ
- スチールラックの追加棚はニトリにある?
スチールラックの棚板の種類と選び方
の棚を自作で増やす-。11-1024x671.jpg)
ストウデン・イメージ
棚板を増やすには「純正パーツを購入する」か「自作する」かの二つです。どちらを選ぶかは、求める耐荷重・デザイン・コスト・加工の手間によって決まります。まず代表的な棚板の種類と特徴を押さえておくと、余計な買い直しを避けやすくなります。
市販の代表例はワイヤーシェルフ、ソリッドシェルフ(平板タイプ)、ウッドシェルフの三つです。ワイヤーシェルフは格子状で通気性が高く湿気がこもりにくい一方、すき間から細かい物が落ちやすい点がデメリットです。
ソリッドシェルフ(金属板)は表面がフラットでコップやプリンターなど不安定な物でも安定し、拭き掃除もしやすい反面、板自体が重く価格もやや高めになりがちです。ウッドシェルフは化粧合板や集成材など木目調の意匠で「見せる収納」に向きますが、金属ほどの防水性がないため水回りでは下敷きシートなどを併用すると長持ちしやすいです。
自作派に人気なのがMDF(中密度繊維板)やOSB、パイン集成材などの板材です。MDFは繊維を圧縮した均一な素材で切断面が欠けにくく塗装もしやすい特性があり、OSBはラフな木片模様でインダストリアルな雰囲気づくりに活躍します。
どちらもホームセンターで入手しやすく、薄い小サイズの板は数百円で購入できる一方、900mm×400mmクラスで厚みが増すと1,000円以上になる例も見られます。多くの店舗では直線カットサービス(1カット数十円程度)を提供しているため、仕上がりを整えたい場合は活用すると効率的です。
耐荷重は棚板そのものよりラック本体の仕様で決まります。ルミナスなど主要ブランドではシリーズごとに棚1枚あたりの耐荷重が公開されているため、公式ページで数値を確認してから電子レンジやオーブンなど重い家電を配置する段を決めると安心です。表示を超える使い方はたわみや破損につながる可能性があるため避けてください。
仕上げの観点では、ワイヤーシェルフの上に自作板を載せる「ハイブリッド」も有効です。格子の段差に合わせて板裏へ細い当て木を接着するとズレにくく、取り外しも容易です。余った棚板は切断してハーフサイズにしサイド収納やノートPC置き場へ転用するなど再利用の幅も広がります。
ポイント:重い家電中心なら耐荷重表示を最優先。見た目を整えたい場合はウッドや自作板にリメイクシートを組み合わせるとバランスが良いです。迷ったらワイヤー+自作板の構成で柔軟性を確保すると長く使いやすいですね。
| 種類 | 長所 | 短所 | 向いている用途 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー | 通気性・価格が安い | 小物が落ちやすい | 家電・大型収納 |
| ソリッド(金属板) | 平面で安定 | やや高価・重い | 食品ストック・調理器具 |
| ウッド | おしゃれ・撮影映え | 水濡れに注意 | リビング雑貨 |
| 自作(MDF等) | サイズ自由・低コスト | 加工手間がかかる | 既製品が合わない場合 |
このように種類ごとの性質を把握しておくと、購入と加工の判断がしやすくなります。余った棚板は補助脚や高さ調整材として活かせるため、捨てずに保管しておくと後で役立つケースが多いです。
棚板を100均素材で作る方法
の棚を自作で増やす-。9-1024x675.jpg)
ストウデン・イメージ
低コストで短時間に仕上げたいときは、100均素材を使った自作棚板が便利です。代表的な素材はカラーボード(発泡素材)、PPシート(ポリプロピレン板)、リメイクシート、布テープなどで、どれも工具をほとんど使わず加工できます。カラーボードは45cm×84cm程度の大判サイズが販売されている例があり、幅60cm前後のラックなら一枚から複数面を切り出せる場合もあります。軽さゆえにカッターで曲線加工しやすいのも利点です。
作り方の基本手順は次の通りです。ラックの内寸を測り、カラーボードに鉛筆で輪郭線を描きます。四隅は支柱径よりわずかに小さく四角く切り欠くと支柱に沿ってはまり込みズレにくくなります。切断は一度に力を入れず複数回軽くなぞるとエッジが崩れません。
裏面に同形状の段ボールを貼り合わせ、周囲を布テープで巻けば二層サンドイッチ構造となり単層よりもたわみにくくなります。布テープはほつれ防止も兼ねるため省略しない方が安定です。
表面仕上げにはリメイクシートが手軽です。木目調や大理石柄を貼るだけで見た目が整い、汚れも拭き取りやすくなります。端は裏へ折り込み、角は斜めカット後に折ると重なりがすっきりします。耐久性をさらに上げたい場合、カラーボードの上に薄いMDF(3mm前後)を重ねる二層構造もおすすめです。100均素材のみで荷重が不安な用途への補強になります。
注意点として、カラーボードは尖った物で表面が凹みやすい性質があります。包丁や金属製フライパンを頻繁に置く段には不向きです。また、電子レンジ・炊飯器など発熱する家電を直接載せると変形する恐れがあるため、耐熱性の高い金属棚板や厚めのMDFへ切り替えてください。
重さ5kgを超える物を複数置くなど長期荷重でも徐々にたわみが出やすいです。こうした制約を理解した上で、小物類・軽量ボックス・コレクション品などを載せる段に活用するとコストパフォーマンスが高くなります。
注意点:100均素材は“仮の棚板”あるいは“軽量物用”と割り切るのが安全です。発熱や加重が大きい用途では、耐荷重が明記された純正棚板への置き換えを検討してください。
費用目安はカラーボード1枚・布テープ・リメイクシートを合わせても数百円〜と低く、純正棚板(サイズや種類により2,000〜5,000円程度が一般的)と比較して大きな節約が期待できます。短時間で見た目を整えたい場合の入り口としても取り組みやすい方法です。
棚を自作する前の採寸手順
の棚を自作で増やす-。8-1024x664.jpg)
ストウデン・イメージ
採寸が不正確だと、完成後にガタつき・浮き・支柱との干渉が起きやすくなります。ここでは自作前に実施したい採寸ステップを整理します。少し丁寧に行うだけで失敗が大幅に減るので、作業開始前に落ち着いて進めてください。
1. 内寸(幅・奥行)を測る:メジャーを棚段の内側に当て、ワイヤー立ち上がり部の内側〜内側までを測ります。外寸を基準にすると板が入らない、あるいは浮いてしまう原因になるため注意が必要です。端数は1mm単位でメモし、切断時は−1〜2mm程度余裕を引くと着脱しやすくなります。
2. 支柱径を測る:デジタルノギスが理想ですが、紙を巻いて周長を測り円周率で割る方法でも概算できます。家庭用ラックでは直径19mmや25mmなど複数規格があるため、ここを誤ると切り欠きサイズが合わず加工し直しになります。
3. 棚段ごとの水平確認:ポールのわずかな歪みや床の傾きで水平が狂う場合があります。水平器(100均でも入手可能)を棚段に置き、泡が中央にあるか確認しておくと後の調整が楽です。軽微な傾きならアジャスターで補正できます。
4. 板厚の選び方:MDFなら5mm厚は軽量物向け、重い家電なら9〜12mm厚を検討します。厚すぎると切断が大変になり、薄すぎると中央がたわみやすいため、用途に応じて中間厚を選ぶと扱いやすいです。
5. 型紙で試作:新聞紙や段ボールで原寸大の型紙を切り、ラックに仮置きして支柱との接触・奥行きの余りを確認します。ここで微調整してから本番素材を加工すれば材料ロスを最小化できます。
採寸メモは棚段ごとに番号を振って整理すると混乱しません。家族と共有する場合は写真に書き込む方法も分かりやすいです。余った棚板を定規代わりに内寸へ当てて直接写し取る方法も精度が出やすく便利です。
最後に安全面です。切断作業時は軍手やカッターマットを用意し、刃を引く方向に体を置かないよう気を付けてください。粉塵が出るMDFやOSBを切る際は屋外または換気の良い場所で行い、マスクを着用すると作業が楽になります。こうした下準備を整えてから本加工に移れば、完成度がぐっと高まります。
▶ ルミナスシリーズの直営サイトだから可能なアウトレットセール開催中! ![]()
棚増設を支えるDIYパーツ
の棚を自作で増やす-。7-1024x677.jpg)
ストウデン・イメージ
自作棚板だけでは安定性や使い勝手が不足する場面があります。そこで活躍するのが各種DIYパーツです。以下では代表的なパーツの役割と使い分けを整理します。名称や互換性はブランドごとに差が出るため、購入前にポール径・シリーズ名・耐荷重を公式情報で確認してください。
コの字バー:左右のポールを水平につないで剛性を高める補強部材です。下段の棚板を外してゴミ箱や洗濯機を収める“空間活用”構成にするとき、横揺れ防止として有効です。取り付けはスリーブを所定位置に装着し、バーを差し込んでゴムハンマーで軽く固定するだけとシンプルです。
ハンガーポール:衣類やバッグを掛けられる棒状パーツでクローゼット代わりに使えます。二本を平行に配置して段差を付けると収納量が増えます。重量が偏らないようコート類は分散させてください。
ワイヤーバー/サポート柵:棚の側面・背面に取り付ける落下防止用パーツです。書籍やファイルケースが横倒れしにくくなり、ディバイダ(仕切り板)と併用するとカテゴリ分けが明確になります。
スライドシェルフ(スライドレール):家電やプリンターを手前に引き出せるレール付き棚です。奥行きが浅いキッチンやデスク周りで整備性を高めます。レール自体に耐荷重が設定されているため、公式表示を超える重量物は載せないでください。
キャスター/アジャスター:移動掃除や模様替えを重視するならキャスター、据え置きで水平調整したいならアジャスターを選びます。キャスターはロック機構付きタイプを使うと安全性が向上します。床材の傷が心配な場合はゴム製キャスターや保護マットを併用すると安心です。
そのほか、パンチングボードやハーフシェルフなどのオプションもあります。パンチングボードにフックを組み合わせれば壁面収納風にアレンジでき、余った棚板を半分に切って側面へハーフシェルフとして追加すれば調味料・リモコンの“小さな定位置”を作れます。
豆知識:余った棚板をL字に切り、金具で固定するとノートPCやルーター用のコーナー棚に再利用できます。不要になったパーツも寸法を測ってから活用方法を検討すると節約につながります。
パーツを増やしすぎるとコストが膨らむため、目的を明確にして優先順位を決めてから導入することが大切です。組み付け時はゴムハンマーを使い、金属ハンマーで直接叩いてコーティングを傷めないよう注意してください。
スチールラックの追加棚はニトリにある?

ニトリ・公式
ニトリで追加棚だけ購入して既存ラックに足したい、という人も多いです。ニトリ公式オンラインストアでは、シリーズによって追加用スチールラック棚板(例:幅や奥行きを合わせた専用棚)が単品販売されているケースがあり、2025年時点では1,500〜2,000円前後の商品も確認できます。ただし他社ラックへ流用できるかは別問題です。
互換性を判断する主な要素はポール径・スリーブ形状・棚板の固定方式です。見た目が似ていても溝角度やパーツ寸法が異なると確実に固定できず、荷重時にずり落ちる恐れがあります。安全面から多くのメーカーが「同シリーズ内での組み合わせ」を推奨しており、店頭で現物を合わせるか型番を控えて問い合わせると失敗を避けやすいです。
もしサイズが合う純正棚板が見つからない場合は、自作が現実的な解決策になります。前述のMDFやカラーボードを用いれば既存フレームに合わせた寸法へ調整可能です。色味をそろえたいときはリメイクシートを全段に貼り、統一感を出せば“別メーカー混在”も目立ちにくくなります。
コスト面では、ニトリの追加棚が1,500円前後から入手できる一方、他ブランド(例:ルミナス)の純正棚板はサイズや種類により2,000〜5,000円以上の価格帯が一般的です。自作MDF板は薄い小サイズなら数百円で調達できるものの、900mm×400mm前後で厚みがある板は1,000円以上になるケースもあるため、材料費と加工時間を含めて比較検討すると判断しやすいでしょう。耐荷重が重要な段のみ純正、軽量物用は自作という併用も合理的です。
追加棚を取り付けた後はスリーブやネジの締め付け状態、棚の水平を必ず点検してください。わずかな傾きでも荷重が偏り寿命を縮める原因になるため、水平器で確認し必要に応じてアジャスターを調整すると安心です。
メタルラック(スチールラック)の棚板を自作で増やす方法
の棚を自作で増やす-。2-1024x683.jpg)
ストウデン・イメージ
- ラックをおしゃれに改造するには
- スライド棚を後付けする
- 棚下にはバスケット設置で小物収納力UP
- ルミナスのスチールラックについて
- 総括:メタルラック(スチールラック)の棚を自作で増やす
ラックをおしゃれに改造するには
の棚を自作で増やす-。5-1024x688.jpg)
ストウデン・イメージ
機能面の改善だけでなく「生活感を抑えてインテリアになじませたい」というニーズも多いです。ここでは簡単に実践できるおしゃれ改造の考え方と、失敗しにくい配色・素材選びをまとめます。ポイントは色・素材・高さの統一です。無秩序にパーツを足すよりも、共通ルールを決めて揃える方がすっきり見えます。
まず色です。フレームがブラックの場合はウォルナット調や濃いグレー系、ホワイトフレームならオークやメープルなど明るい木目が相性が良い傾向があります。これは暗い色+中〜明るい木目のコントラストで立体感が出るためです。自作棚板を塗装する場合、水性塗料を薄く2回塗って乾かし、仕上げにクリアワックスを薄く伸ばすと汚れが染み込みにくくなります。水性塗料は扱いやすく、室内でも比較的臭いが少ないとされています。
リメイクシートを使う場合は、光の反射が強すぎないマットタイプを選ぶと指紋やホコリが目立ちにくいです。貼り方は中央から外側へヘラで空気を押し出し、角はドライヤーで温めてから折り込むとシワが出にくくなります。剥がす際に糊が残りにくいシートも増えているため、賃貸の家具アレンジにも向いています。
ワイヤー棚の隙間を埋めて小物を安定させたい場合、透明のビニールシートや薄いMDFを敷くと機能面と見た目を両立できます。透明シートは圧迫感が少なく、下段の影が抜けることで軽やかな印象を保てます。小物収納には統一色のボックスを並べる方法が定番です。ラベルプレートを前面に貼ると分類が一目でわかり、家族との共有もしやすいですよ。
照明を加えるアレンジも効果的です。USB給電のテープライトを棚裏に貼ると、夜間でも中身が見やすくフォトジェニックな雰囲気になります。熱量が少ないLEDを選び、コードは結束バンドでポール沿いにまとめると安全です。さらに観葉植物やフレームアートを上段に置くと“収納家具”から“飾る家具”へ印象が変わります。
おすすめ配色例:ブラックフレーム+ウォルナット調板/ホワイトフレーム+明るいナチュラル木目。差し色としてグリーン(植物)や真鍮小物を一つ入れるとまとまりやすいです。
メンテナンスも重要です。ウッド調表面は乾いた布でこまめにホコリを拭き、こぼれた液体は早めに拭き取ると長持ちします。前述の方法を組み合わせれば、既存ラックでも低コストでおしゃれな印象に仕上げられますね。
キッチンにメタルラックを導入 pic.twitter.com/0PIBv6t0L3
— 三好草平 (@HummingBird1979) May 3, 2024
スライド棚を後付けする
の棚を自作で増やす-。4-1024x752.jpg)
ストウデン・イメージ
スライド棚は電子レンジ・炊飯器・プリンターなど奥行きのある機器を手前に引き出して使えるようにする後付け機構です。天板上で蒸気がこもる、奥が拭き掃除しにくいといった悩みを解消し、日常の動作をスムーズにします。ここでは一般的な取り付け手順と注意点を詳しく説明します。
まず対応レールパーツを用意します。ブランドごとにレール幅・固定方法が異なるため、ポール径と棚幅が一致するか型番で確認してください。レールには耐荷重が明記されているので、想定する家電重量(取扱説明書に記載)と比較し上回らないようにします。耐荷重に余裕を持たせると滑りが安定しやすいですね。
取り付け準備
設置したい段の高さを決め、周囲の収納物を一度取り外します。ポールにスリーブ(樹脂のリング)を指定高さへ取り付け、左右の高さが揃っているかメジャーか水平器で確認します。ここでズレがあるとレールが歪み、引き出し時に引っかかる原因になります。
レール固定と棚板装着
スリーブの上からレールを差し込み、必要に応じてネジやピンで仮固定します。その上に棚板(純正ソリッドシェルフや自作MDF)を載せ、前後へゆっくり動かして抵抗感を確認します。重心が前に動くため、ラック全体が前傾しないか下段へ重量物を配置してバランスを取ると安全です。家電を置く前に空の状態で複数回スライドさせ、異音やガタつきがないか点検してください。
注意:スライド棚を最大まで引き出した状態で放置すると、荷重が片側に集中して転倒リスクが高まります。使用後は必ず押し戻し、ロック機構がある場合は固定しておきましょう。耐荷重表記を超える設置は避けてください。
オプションとして耐熱マットを敷くと、炊飯器の蒸気による棚板の劣化を抑えられます。コードはケーブルクリップで棚裏に沿わせると動作時に引っかかりにくくなります。こうした工夫により、限られた奥行きでも快適な“引き出せる収納”へ変えられます。
また、スライド棚は引き出し時に重心が前へ移動するため、総務省消防庁が解説する家具固定の基本(L型金具や突っ張り器具の活用)も併せて確認しておくと安心です。
(参考:総務省消防庁「地震による家具の転倒を防ぐには」)
棚下にはバスケット設置で小物収納力UP
の棚を自作で増やす-。3-1024x678.jpg)
ストウデン・イメージ
棚下バスケットはワイヤー棚の下面に差し込んで使う後付けパーツで、空いている“空間”を引き出し風に活用できるアイテムです。工具不要で装着でき、取り外しも簡単なので模様替えの頻度が高い家庭にも向いています。ここでは効果的な活用シーンと選び方のコツを紹介します。
活用しやすいのはカトラリー・レシピカード・文房具・予備の電池など、頻繁に使うけれど散らばりやすい小物です。ワイヤー棚の格子にフック部分を引っ掛けるだけで固定でき、下段の収納物に干渉しない高さを選べばデッドスペースが効率的な“浮かせる収納”へ変わります。幅は棚板より少し短いものを選ぶと、左右に余白が生まれて圧迫感を抑えられます。
選び方のポイントはサイズ・耐荷重・通気性です。まず棚板下面から下段アイテムまでの高さを測り、バスケットの深さを決めます。深すぎると下段とぶつかり、浅すぎると収納力が不足します。耐荷重はメーカー表記を参考にし、ガラス瓶など重い物は避け軽量物に絞ると変形しにくいです。メッシュ状タイプならホコリが溜まりにくく、食品包装の一時置きにも向いています。
複数並べる場合はラベルシールで分類を明示すると探索時間が減ります。色はラックや棚板と同系色にするか、グレー・ホワイトなどニュートラルカラーで統一すると雑多な印象が薄れます。不要になったら外して水洗いできる商品も多く、衛生面でも管理しやすいですね。
さらに応用例として、バスケット前面にS字フックを掛けて輪ゴム・鍋つかみを吊るすと細かな定位置が増えます。こうした“足し算の収納”は増やし過ぎると視界がうるさくなるため、使用頻度の高いものを優先し、定期的に中身を見直すと快適さを保てます。
ルミナスのスチールラックについて

ルミナス・公式
ルミナスのスチールラックは国内で広く流通しており、サイズ展開やオプションパーツの豊富さが特徴とされています。公式サイトによると銀色フレームには防錆クリアコーティングが施されていると案内されており、水回り環境でも使用しやすい点が支持されています。ここでは自作棚板と組み合わせる際のポイントを整理します。
まずポール径です。一般的なシリーズでは25mmや19mmなど複数の規格が存在し、棚板・スリーブも径に合わせた専用品になっています。自作板を載せる場合はポール間内寸を正確に測り、支柱干渉部分を切り欠く加工を行えば純正棚と同様に安定させやすいです。ワイヤー棚に自作板を載せる場合、裏面に細い当て木を接着して“落とし込み”構造を作るとズレ防止になります。
オプションパーツはDIY自由度を高めます。パンチングボードを縦に連結して壁面収納風にしたり、延長ポールで天井近くまで高さを拡張し突っ張り式収納として活用することも可能です。耐荷重や組み合わせ可否は公式カタログで個別に明記されているため、複数パーツを同時に導入する前に確認してください。安全のため重量物は下段、軽量物と装飾品は上段へ配置する基本ルールを守るとバランスが安定します。
コスト面では、全段を純正ウッドシェルフにするより下段はワイヤー+自作MDF、目線より上だけ純正ウッドというミックス構成が費用対効果に優れます。見せたい段を重点的に投資し、それ以外を自作で補う考え方ですね。こうした柔軟性がルミナスをベースにしたDIYの強みと言えます。
▶ ルミナスシリーズの直営サイトだから可能なアウトレットセール開催中! ![]()
総括:メタルラック(スチールラック)の棚を自作で増やす
市販パーツと自作板材をバランスよく組み合わせれば、見た目・強度・コストの三つを無理なく両立できます。ポイントは「適正耐荷重の把握」「寸法精度」「パーツ互換性の確認」の三つです。
特に追加棚やレール類はメーカーごとに規格が異なるため、ポール径やスリーブ形状を必ず確認しましょう。薄い小サイズ板なら数百円で自作できますが、厚手の大判MDFは1,000円以上に上るケースもあります。こうした価格差を踏まえ、重い段は純正、軽量段は自作など段ごとに役割を分けるとコスト効率が高まります。
- 純正棚板はワイヤー・ソリッド・ウッドから用途別に選ぶ
- 小型の100均素材は低コストだが重荷重と高温には不向き
- 採寸は内寸とポール径(25・19・12.7mm)を正確に測る
- 余った棚板はカットしてハーフシェルフや補助材に再利用
- コの字バーやサポート柵で横揺れと落下を防止できる
- ニトリ追加棚は1,500円前後の小型が多く互換は要確認
- リメイクシートと水性塗料で色調を統一し生活感を抑える
- スライドシェルフ後付けで電子レンジやプリンターを引き出せる
- 棚下バスケットで空間を“引き出し化”して小物を整理
- ルミナスはパーツが400種以上あり拡張プランが立てやすい
- ワイヤー棚のすき間対策に透明シートや薄板を敷く
- 耐荷重表示を超えない範囲で重い物は下段へ配置
- 塗装後のワックス仕上げで汚れと水染みを防止
- 水平器とアジャスターで微妙な傾きを早めに調整
- 純正+自作の“ハイブリッド構成”で費用と機能を最適化
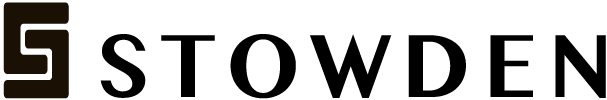
の棚を自作で増やす-。12.jpg)